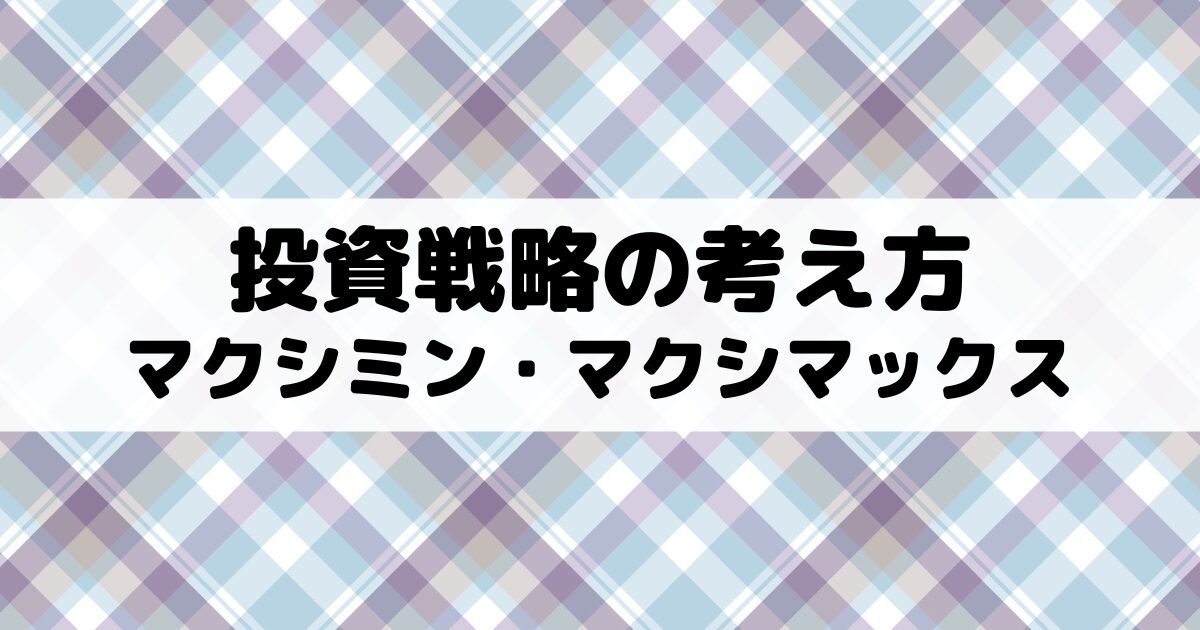投資に対する「考え方」や「戦略」は人それぞれ異なります。「短期で大きな利益を狙いたい」、「長期でじっくりと利益を狙いたい」。ある程度リスクが取れる、リスクは出来るだけ取りたくないなど。
今回は投資戦略の「マクシミン原理」と「マクシマックス原理」を確認して、投資に対する考え・実践について見ていきます。あくまでも「このような考え方がある」と言う話です。
- あくまでも考え方で正解は無い
- 多くの考え方を知ることで選択肢を増やすことが出来る
- 自分に合った投資法を見つけるのが最適解
意思決定と行動選択について
投資の方向性や方針を決めるのが「意思決定」、実際に行動に移すことが「行動選択」です。
「方針を決めない(意思決定をしない)」、「方針を守らない(行動選択を間違う)」のは「投資でやっていけない事」とされています。
意思決定
「マクシミン原理」は「最低限確保できる利益が最大になる」守りの考え、「マクシマックス原理」は「利益が最大化する可能性がある」攻めの考えです。
マクシミン原理(maximin-priciple)とは
マクシミン原理は「最低限獲得できる利益が一番大きくなるであろう戦略」です。手堅いコツコツ戦略ともいえます。
例えば、10万円で購入できる株式銘柄が3種類あるとします。為替の影響で下記のように株価が変動すると仮定したケースを考えてみます。
| 株式 | 円高 | 円安 |
|---|---|---|
| A銘柄 | 15万円(+5万円) | 8万円(-2万円) |
| B銘柄 | 13万円(+3万円) | 12万円(+2万円) |
| C銘柄 | 5万円(-5万円) | 20万円(+10万円) |
円高、円安どちらに動いても、最低でも+2万円を確保できるB銘柄を購入するのが「マクシミン原理」です。
マクシマックス原理(maximax-priciple)とは
マクシマックス原理は「利益が最大化する可能性がある戦略」です。リスクを恐れない積極的な戦略ともいえます。上記と同じ条件の場合、+10万円が狙えるC銘柄を購入するのが「マクシマックス原理」です。
実際の株価はもっと複雑
当然ですが実際の株価は為替の影響だけでは決まらずもっと複雑です。あくまでも「ある程度予測できる将来の出来事に対する」基本的な考え方の一つです。
原理を応用して実際に利用する例
相場全体が大きく下落した場合を想定します。株価が大きく下落した場合、その後の株式相場全体として想定される動きは「更に下落する」、「下落も上昇もせず緩やかに推移する」、「上昇する」のいずれかとなります。
マクシミンの例
「更に下落するか」、「上昇するか」どちらに転んでもある程度の利益を確保したいという場合は個別銘柄ではなく、余力を残しETFを少し購入、上昇したら売却、下落した場合は幅を持たせゆっくりとナンピンするのがマクシミン原理に近い考えです。
※あくまでも考え方で、必ず利益が出るとは言えないです。ナンピンを想定すると原資も必要です。
マクシマックスの例
「上昇する」と見る場合「買い目線」、「さらに下落する」と見る場合は「売り目線」で入ることで大きな利益が手にできる可能性があります。もちろん、予想が外れた場合は大きく損をする可能性があります。
銘柄別のリスク
リスクが無い銘柄は存在しないですが、銘柄によりリスクの大きさは異なります。
また、マクシミンは最低限利益を確保する戦略ですが、投資で必ずプラスになる選択肢は存在しません。投資とはそういうものです。貯金は必ずプラスになりますが、インフレ率を考えると実質マイナスです。
さいごに
投資は選択の連続です、選択を間違えたと思うことも多々出てきます。
投資活動は売買だけでは無い
同じ失敗を繰り返さないためにもなぜ選択を間違えたのか、どのような狙いでどのような考えだったのかを振り返ることも立派な投資活動の一つです。
売買することだけが投資では無いです。投資について調べたりするのも投資活動の一つです。
選択肢を増やす
多くの戦略や考えを知ることは選択肢を増やすことになります。知識・選択肢が増えたら利益が増えるとは言い切れないですが、正しい知識や多くの選択肢は「間違った選択を防ぐ可能性が高くなります(騙されないようになります)」。
また、「成功した人の戦略を真似する」、「他人任せ」で利益が出るものではないです。あくまでも自分にあった戦略を見つけることが重要です。
投資には「明らかな間違いが存在しますが、正解は人それぞれ」です。